

福岡市民病院救急科は二次救急病院であり、主に二次救急患者の対応を担っておりますが、重度の意識障害、ショックバイタル、重症低酸素血症や心肺停止などの三次救急患者の受け入れにも柔軟に対応しております。
また、何も考えずに全ての患者を受け入れるというわけではなく、救急隊からの受け入れ要請時の情報で、明らかに初めから他院へ搬送した方が患者の利益になると判断した際には、該当診療科のある病院への搬送をすすめる様、救急隊に助言し適切なトリアージに努めています。
医師の持つホットラインで救急隊から傷病者を受け入れ、各科医師の協力のもと診療、治療を速やかに開始しています。
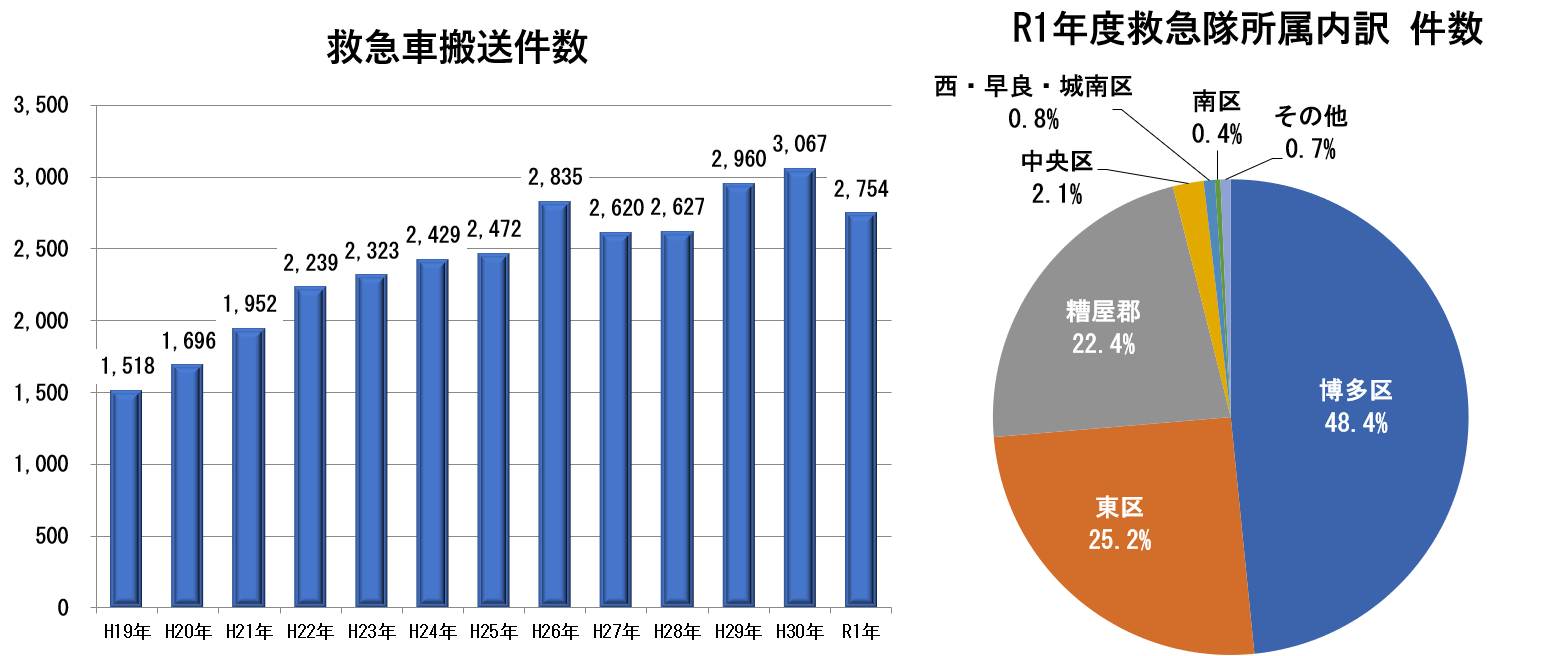
主に平時の診療時間外に当院受診を強く望まれる徒歩来院救急患者を救急外来で対応しています。令和元年度は2,033例の受診がありました。診療体制ですが、研修医が救急科医師や当番医師の指導のもと診療にあたります。
徒歩来院患者は、大部分が診察後帰宅可能な一次救急患者ですが、一部(23.5%)は入院が必要な二次救急患者であり、稀に緊急で対応が必要な三次救急患者も徒歩来院されています。多くの患者で溢れる救急外来で、徒歩来院された患者の中から重症患者をピックアップすることは容易ではありません。そこで当院では患者の安全に配慮して院内トリアージシステムを取り入れています。徒歩来院患者の外来待ち時間に、看護師(トリアージナース)が患者の緊急度と重症度を判断し治療優先順位を判断するとともに看護介入を開始するようにしています。
当院は主にいわゆる北米型ER(初療対応、患者振り分け)の形をとっていますが、入院患者も受け持って対応しています。多科にまたがるような疾患を合併している患者や軽症薬物中毒、原因不詳の意識障害などの救急科特有の疾患まで幅広く診療させて頂いています。必要時、適宜各診療科にコンサルトを行い、質の高い治療を提供できる様に努めています。
当院の集中治療室は4床のベッドがあり、システムはいわゆるopen ICUで、入室した患者の担当診療科が主となり診療しています。救急科医師2名とも救急専門医であると同時に集中治療専門医であり、高度な集中治療への対応が可能です。集中治療専門医が全ての全身管理を行なうICU、いわゆるclosed ICUの患者予後が良好であることは数多の報告がありますが、マンパワーの問題から、止むを得ずopen ICUの形としております。常時、担当診療科からの相談には応じ、可能な限り診療に協力しております。重症薬物中毒、敗血症、心肺停止蘇生後症候群などの患者は当科で診療しております。研修医への集中治療指導も積極的に行っています。
院内で発生する心停止患者への対応だけでなく、バイタルサインの変化に対し早めに対応することで心停止に至る患者を減らすためにRapid Response System(RRS)を導入する施設が増加していますが、当院も平成27年8月より導入いたしました。徐々に要請件数は増加していましたが、ここ3年は減少傾向にあります。院内急変症例(ハリーコール)も減少傾向であり、RRS要請よりもさらに前の段階で対応が出来ているため、より患者の重症化予防が出来ていると考えています。
教育の面では、質の高い救急医療の提供と院内の患者安全のために、院内全職員を対象にBLS講習会を毎年開催し、指導は救急科医師、救急部看護師が中心となって行い、2年に1回の受講を義務付けています。
今年から救急専門医2名での対応となります。2名とも福岡県以外での救急医療経験が豊富です。その経験を生かし、福岡県の救急医療体制の問題点改善に少しでも貢献できる様、努力していく所存です。
≪当院の救急診療体制等について詳しくは下記に掲載しています≫